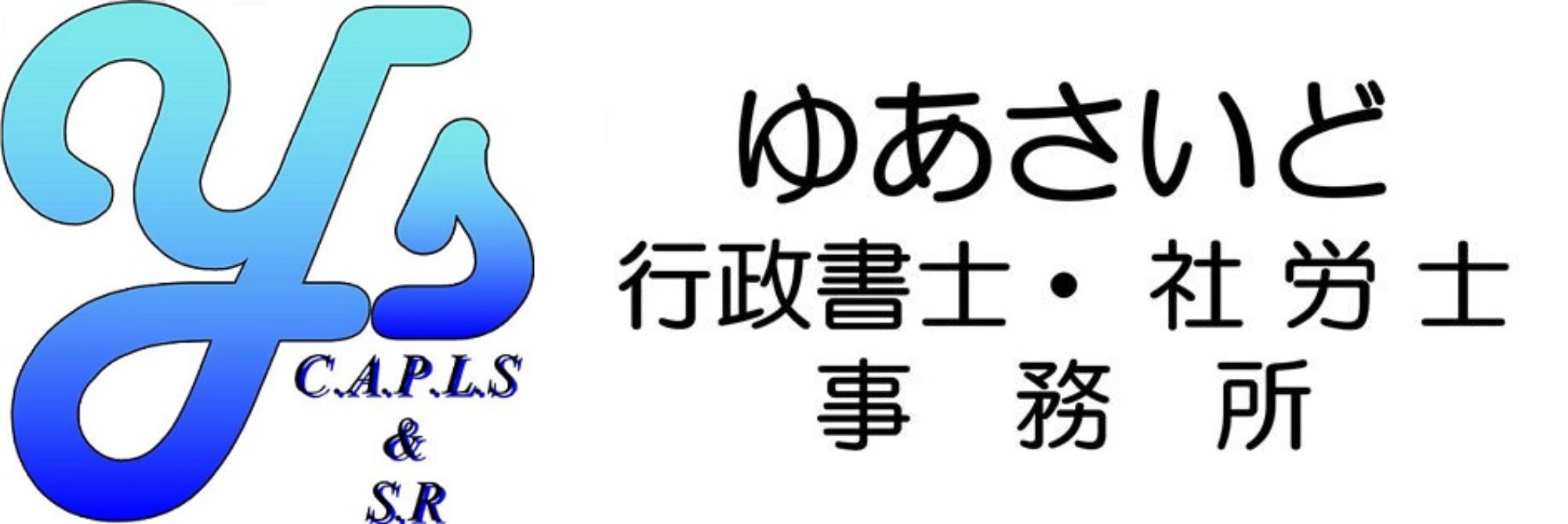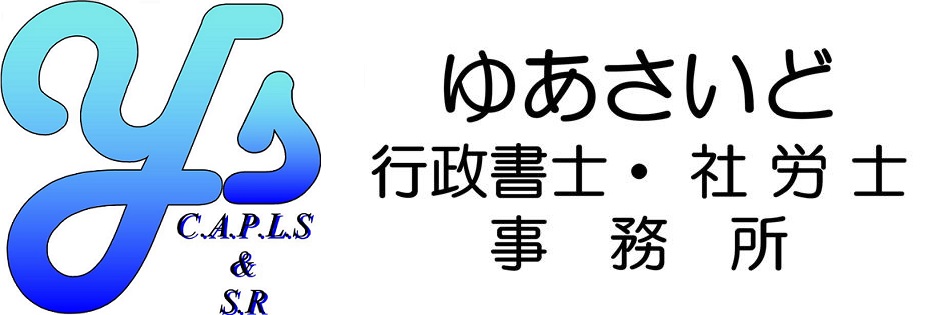まずは気になる情報から
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・建設業の担い手確保を推進するため、改正建設業法の一部を施行します
~「労務費の基準」や工事契約内容に関する調査を建設業法に位置づけ~
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
国土交通省ホームページより
建設業の担い手確保を推進するため、改正建設業法の一部を施行します
~「労務費の基準」や工事契約内容に関する調査を建設業法に位置づけ~
として報道発表されています。
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo13_hh_000001_00250.html
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・在留資格「特定活動」(デジタルノマド(国際的なリモートワーク等を目的として本邦に滞在する者)及びその配偶者・子)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
入管庁ホームページより
在留資格「特定活動」(デジタルノマド(国際的なリモートワーク等を目的として本邦に滞在する者)及びその配偶者・子)
の情報が更新されています。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities10_00001.html
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・(入管庁)お盆期間における開閉庁日案内
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
入管庁ホームページより
お盆期間における開閉庁日案内
が掲載されています。
https://www.moj.go.jp/isa/01_00462.html
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・林業職種の育林・素材生産作業について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種
及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等についての意見・情報の募集について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
林業職種の育林・素材生産作業について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等についてパブリックコメントが実施されています。
実施期間
2024年7月26日から同9月1日
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550003974&Mode=0
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントが実施されています。
実施期間
2024年7月26日から同8月31日
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240098&Mode=0
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める特定の職種及び作業の一部を改正する件(案)に関する御意見の募集について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める特定の職種及び作業の一部を改正する件(案)に関するパブリックコメントが実施されています。
実施期間
2024年7月26日から同8月31日
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240104&Mode=0
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・「長さが21メートルを超えるフルトレーラ連結車に係る特殊車両の通行許可の取扱いについて」の一部改正(ダブル連結トラックの対象路線の拡充)に関する意見募集について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
「長さが21メートルを超えるフルトレーラ連結車に係る特殊車両の通行許可の取扱いについて」の一部改正(ダブル連結トラックの対象路線の拡充)に関するパブリックコメントが実施されています。
実施期間
2024年7月25日から同9月2日
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155240603&Mode=0
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき飲食料品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準の一部を改正する件
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
官報 令和6年7月23日(本紙 第1269号)にて
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき飲食料品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準の一部を改正する件
が告示され同日施行されています。
夏も本番となり、本当に暑い日が続いています。
あとどれだけ続くのか、、、
さて、皆さんはこの暑さで体調を崩したりはしていませんか?
熱中症、脱水症状、食中毒などが起こりやすい季節です。
無理をしないことも大事ですよね!
そこで今回は、食中毒に関して少し投稿したいと思います。
自宅で調理して食べたことによる食中毒はある意味自己責任の話ですが、外食をした際はどうでしょう?
そう単純ではありませんよね?
複数の症例が確認できないと、どこで起こったのかを特定するのも難しいです。
場合によっては、水筒やペットボトルに口をつけ、長時間経つことで雑菌が増えて食中毒を起こすこともあります。
この場合は、製造元に責任はありませんよね?
飲食店はどうでしょう?
ちょうど先日うなぎ屋で食中毒が発生したようです。
ウナギは基本「焼く」「蒸す」などの加熱処理が行われますので、一般的な雑菌はそこで死滅するでしょう。
しかし、まな板の使いまわしや包丁の使いまわしにより、せっかく加熱処理で死滅しているうなぎに、雑菌をつけてしまうこともあります。
そして、飲食店が食中毒を起こすと、しばらくの間「営業停止」処分がなされます。
夏休みも始まりかき入れ時の営業停止は厳しいですよね?
私のお客さんのお店では、夏場は生ものは出さないようにしているお店もあります。
が、上記の通り、まな板や包丁の使いまわしで食中毒は発生しえますので、その辺の対応はしっかり行わなければいけません。
焼き肉店もそうですね(バーベキューも同じでしょう)
加熱前の肉を触る箸やトングと、焼けた後の肉を触る箸やトングは別にしないと、焼く前の肉の雑菌を焼けた後の肉に付けることになります。
せっかくの夏休みですから
熱中症、脱水症状、食中毒に気を付けて、楽しくお過ごしください。